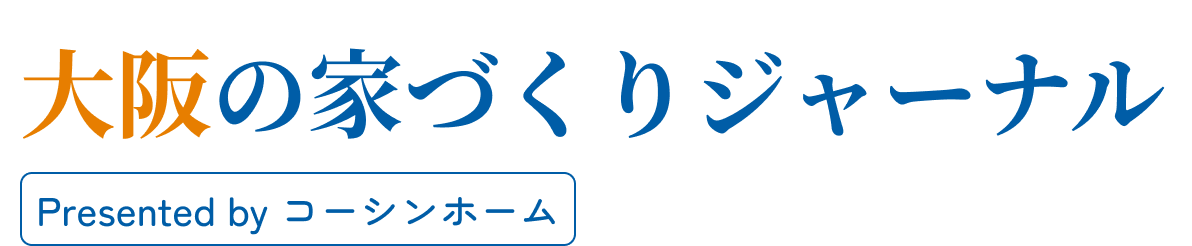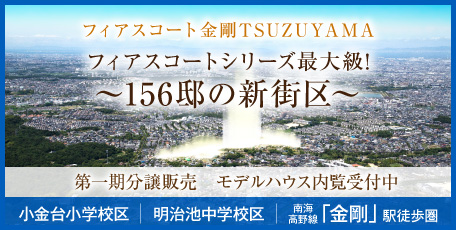1. はじめに 〜「家をどうする?」が離婚時の大きなテーマに
離婚を考えたとき、避けて通れないのが「住まいの整理」。
特に大阪狭山市のように戸建住宅の多い地域では、マイホームの扱いがトラブルの原因になることも少なくありません。
- 住宅ローンが残っているが、どちらが住む?
- 売るべきか?貸すべきか?
- 名義はどうなっている?
- 相手が住んだままで、自分は支払いだけしている…
このような問題は、感情的なもつれと同時に、資産・法的な整理が求められる非常に複雑なテーマです。
だからこそ、まずは“今の家の価値”を正確に把握することが、冷静な判断を下す第一歩となります。
2. 離婚と不動産の整理でよくある3つの悩み
離婚をきっかけに「家をどうするか」という問題に直面したとき、多くの方が以下の3つの壁にぶつかります。どれも感情面だけでなく、法的・経済的な視点から慎重に整理が必要なテーマです。
◾ 1. ローンが残っている場合の対処
夫婦で家を購入した際、多くのケースで住宅ローンが残っている状態です。
- 「今売ってもローンが残るのでは?」
- 「どちらがローンを払い続けるのか決まっていない」
- 「ローン名義が元配偶者で支払いは自分」という複雑な状態も
こうした場合、まず必要なのは家の“現在の価値”を知ること。査定を行えば、売却によってローンを完済できるのか、それとも任意売却や他の方法を検討するべきかが見えてきます。
◾ 2. 共有名義のトラブル
不動産が「共有名義」になっている場合、売却や名義変更には原則として双方の合意が必要になります。
- 「一方は売りたいが、一方は住み続けたい」
- 「名義変更を求めても、相手が応じない」
- 「ローンだけが自分の名義」という偏った負担構造
こうした問題は話し合いが難航しやすく、時間が経つほど精神的な負担も増えていきます。早めの査定と専門家によるアドバイスで、現実的な選択肢を整理しましょう。
◾ 3. 一方が住み続けるケースでの不公平感
子どもや仕事の都合で「元配偶者がそのまま住み続ける」というケースもあります。しかし、以下のような課題が生じやすくなります。
- ローンは支払っているのに、自分は住んでいない
- 名義が共有のままで、資産として動かせない
- 家の維持費や固定資産税などの負担が不公平
このような状態は「将来のトラブルの火種」にもなりかねません。売却して現金化する、名義や支払いの分担を明確にするなど、“整理”という行動が後の安心につながります。
→ 離婚と家の問題は、感情ではなく“数字”と“契約”で整理することが何より重要。まずは査定を通じて、現状を客観的に見つめるところから始めましょう。
3. 査定で“冷静な判断”の土台を作る
離婚時はどうしても感情が先行しやすく、「揉めてから対応する」と、余計に時間とコストがかかるケースも。
無料査定を受けることで…
- 現在の資産価値が明確になる
- 家を売るか、持ち続けるかの判断がしやすくなる
- 売却した場合の手取りシミュレーションで先が見える
→ 感情ではなく、データと客観的な選択肢で今後を考えることができます。
4. 実際の相談事例(大阪狭山市)
【40代女性|共有名義でローン返済中】
離婚後も元夫と共有名義のまま居住。ローンの返済名義が自分だったため、不公平感と将来の不安からご相談。
- 査定により市場価値が想定より高く、売却で残債を完済可能と判明
- 双方の了承のもと、任意売却を実行
- 売却益で新生活のスタート資金を確保
→ 「ようやく気持ちの整理ができた」と新たなスタートを切られました。
5. まとめ 〜 “家の整理”から始める人生のリスタート
離婚は感情的にも体力的にも大きなエネルギーを使います。
だからこそ、“家のこと”を後回しにせず、早めに整理することで、その後の生活をスムーズに整えることができます。
- 家の価値を知る
- 売却 or 保有のメリット・デメリットを比べる
- 新たな住まいの選択肢を探す
「今の家、どうするか?」に対する答えは、査定から見えてきます。
6. ご相談・無料査定のご案内
コーシンホーム株式会社
【本社】〒599-8107 大阪府堺市東区白鷺町1丁5番1-2号
【電話番号】072-240-2150
【なんば支店】〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー19F
【電話番号】06-7662-8768
【公式サイト】https://cohshin-home.com/
→ プライバシーに配慮した対応、机上査定や訪問なしのご相談も可能です。
まずは「知ること」から、未来の一歩を踏み出しましょう。